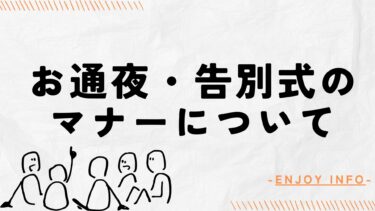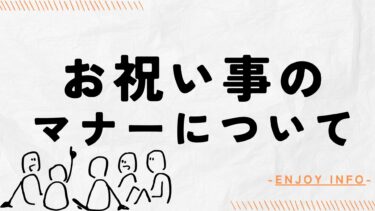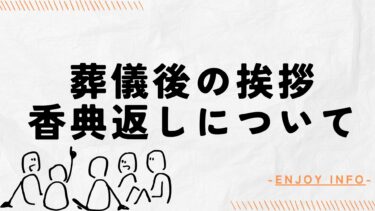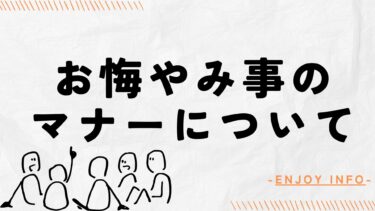仏式の礼拝マナー
お葬式には「仏式」「神式」「キリスト教式」と3つの礼拝方法があります。
まずは、「仏式」の礼拝マナーをみていきましょう。
仏式は数珠を使って礼拝します。
数珠は5種類がありますが、本式は108個、
また宗派により異なりますが一般的には一重の略式の数珠が使われます。
数珠の正しい持ち方はふさを下にして左手で持ちます。
席を離れるときに椅子や畳の上に置くのはマナー違反です。
<線香のあげ方のポイントです>
① 焼香台前に座り遺族、僧侶に一礼し霊前で軽く合掌したのち
右手で線香を1本取り、灯明に近づけて火を移す
② 線香に火がついたら左手で軽くあおいで消す
③ 他の線香と間隔を置いて香炉の奥側に立てる
④ 合掌をし座を下がり遺族、僧侶に一礼をする
お通夜・告別式の服装のマナー
アクセサリーは結婚指輪と真珠(涙を連想させる為)は可能です。
ネックレスなどは一連にしましょう。
二連、三連は「重なる」と連想させる為つけることは出来ません。
焼香のマナー
焼香の際に周りの様子を伺いながら恐る恐る焼香をした経験はありませんか?
故人を偲ぶためのお葬式…別のことでそわそわするのはよろしくないですね。
焼香の仕方も身につけておきましょう。
焼香のマナーは、地域や宗派によって大きく異なります。
事前に宗派などを知ることができた場合、その決まりに合わせます。
例えば…
焼香の仕方は、三本の指で目の高さまであげます。
焼香回数は3回です。それぞれ意味があり、
1回目は仏(亡くなった方)へ、2回目は法(仏の教え)、3回目は僧(僧侶)にです。
【立式焼香】
1、焼香台の2、3歩手前で遺族、僧侶に一礼する
2、前へ進み身を正して遺影に合掌、一礼する
3、後ろ向きに2、3歩下がり再度遺族、僧侶に一礼する
【座礼焼香】
1、腰を屈めて焼香台に向かい、遺族、僧侶に一礼する
2、座布団の前で両手を使って膝立ちし、にじり寄って正座したら遺影に合掌、一礼する
3、焼香後、両手を使って膝立ちし、そのままの姿勢で後退し中腰になったら
遺族、僧侶に一礼をして中腰のまま席に戻る
【回し焼香】
1、隣から回ってきたら軽く会釈をして両手で受け取る
2、自分の前におき、遺影に合掌、一礼する
3、隣の人へ両手で渡す
機会があれば一度自身の宗派や地域のしきたりなどを確認しておくことも大切ですね。
神式の礼拝マナー
神式の場合、数珠は使用せず玉串(榊の枝)を使用しての礼拝です。
玉串を神前にささげ礼拝することを玉串奉奠(たまぐしほうてん)といいます。
玉串奉奠の扱い方は以下の通りです。
1、玉串は枝の根元を右手で、左手は葉の下から掲げもつように受け取る
2、神官に一礼し、祭壇に向かい玉串の枝が自分の方に向くように引き寄せる
3、右手で葉先、左手で枝を支えるように持ち替えて、玉串を時計方向に回す
4、枝側を祭壇に向けたらゆっくりと供え、2~3歩下がって
音を立てないようにしのび手(音を出さない)で二礼二拍手一礼する
また玉串の切れ目を見せないように扱います。
お通夜・告別式でのマナーの基本
まず、お通夜とは親族のための別れの儀式です。
それに対して告別式は一般弔問者のための別れの儀式です。
お通夜での服装は礼服、若しくは地味目でカジュアルでないものを選びます。
葬儀、告別式では葬儀の形式に合わせたしきたりや言葉使いに注意します。
宗派や地域によってもそのマナーは大きく異なります。
例えば仏式以外では「お悔やみ」、「供養」、「焼香」などの言葉は使いません。
また出棺時は待っている間はコートなど上着を着用していてもいいですが、
出棺の時には脱ぐのがマナーです。
また供花、供物についてですが、贈る際は先方に確認する方が好ましいでしょう。
参考までに、葬儀の形式に合った供花、供物をご紹介します。
【供花、供物】
仏式 :線香、ろうそく、果物、菓子
神式 :海産物、酒、和菓子
キリスト教式 :供物は贈らず、白い供花
仏式では魚や肉などの生ものは贈りません。
神式では焼香がないので線香、ろうそくを贈るのもマナー違反です。