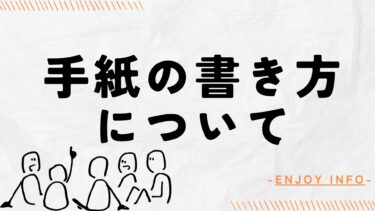年賀状のマナー
新年の挨拶はメールではなく、手書きのメッセージを添えた年賀状を送りたいものです。
まず最初に、年賀状の表書きに関するマナーについて触れたいと思います。
宛先の住所は縦書きの場合、漢数字を用いることが望ましく、
郵便番号も忘れずに記入する必要があります。
宛名は中央に配置し、敬称には『様』を使いますが、
ご家族宛の場合は全員に『様』をつけてください。
また、『年賀』の文字は切手の下に朱色で書くことをお忘れなく。
これがないと通常の郵便として扱われてしまうので注意が必要です。
自分の住所も必ず記入しましょう。
これを書く際は、宛名よりも小さめの文字で表記します。
年賀状は、遅くとも1月3日までには届けたいものですので、
12月中旬から12月24日までの間に投函することが求められます。
写真を添えた年賀状は親しい間柄では喜ばれることが多いですが、
上司や目上の方に送る際には配慮が必要です。
もちろん、相手が不快に感じることや暗い話題、
またネガティブな言葉は避けるべきです。
印刷された年賀状を送る人も多いですが、
たとえ短い一言でも手書きのメッセージを添えることをお勧めします。
意外に起こりやすいミスは、年号を重複して記載してしまうことですので、注意が必要です。
年賀状を出していない方から年賀状が届くこともあります。
その場合、1月7日頃までに届いたら、できるだけ早くお返事をするように心がけましょう。
もし年賀状が届かないようであれば、寒中見舞いを送ると良いでしょう。
また、喪中に年賀状が届いた場合も寒中見舞いを送り、
自分が喪中の際には11月中に喪中欠礼はがきを出しておくことが大切です。
このはがきには、故人の名前や亡くなった日、相手への感謝の意を記載します。
もし相手の喪中に知らずに年賀状を送ってしまった場合は、
速やかにお詫びの連絡を入れることが求められます。
喪中の際には、相手への気遣いがさらに大切です。
年賀状は、日頃お世話になっている方々へのご挨拶です。
枚数が多いと手間がかかりますが、一人一人に心を込めて送りたいものです。
季節の挨拶文のマナー
季節ごとにあいさつのお手紙を出しますが、1つ1つにあいさつ文のマナーがあります。
【年賀状のマナー】
本来は元旦に届くべきものですが、なるべく松の内(1月7日)、もしくは小正月まで(1月15日)ならよしとされています。
やむ終えない事情の場合は「寒中見舞い」で出します。
【寒中見舞いのマナー】
梅雨明けから立秋(8月8日頃)までに出します。
それ以降は「残暑見舞い」で出します。
目上の方に出すときは、「暑中お伺い」とし8月末までに出しましょう。
【寒中見舞いのマナー】
寒の入り(1月15日頃)から立春(2月3日頃)までに出します。
立春以降は「寒中見舞い」とし2月末までに出します。
喪中で欠礼した人にも利用できます。
せっかく心をこめて送るあいさつ状です。マナーを守ってスマートに送りたいですね。