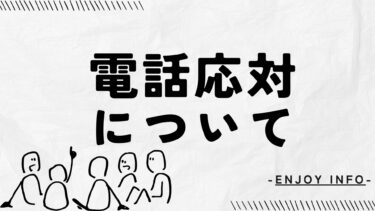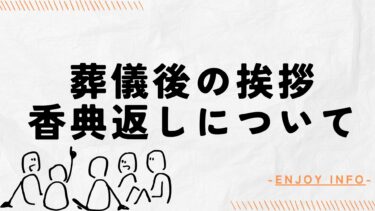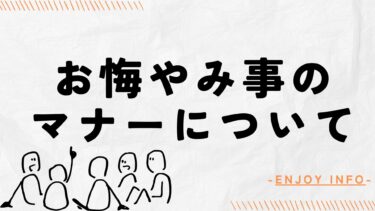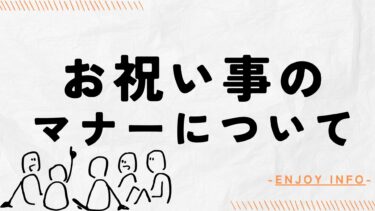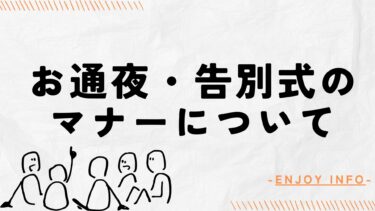お葬式に関する一般的なマナーについて
お葬式で失礼にならないように守るマナーをご紹介いたします。
注意するポイントは多岐に渡るため、当日の服装から挨拶の言葉まで、参列にあたり不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
自分が不安な点を確認(弔問、香典、焼香など)して事前に不安を払拭しスムーズに参列できるようにしましょう。
また、お葬式のパターン(通夜・葬式・葬儀)の違いもあわせて解説します。
遺族の悲しみを増幅させたり、不快な思いをさせたりしない意識が大切です。お葬式に参列する際は、基本的なマナーを理解し、気持ちよく故人を送り出しましょう。お葬式にはいくつかの段階や種類があり、それぞれでマナーが異なることがあります。
通夜・葬式・葬儀の違い
亡くなった方を弔う儀式にはその儀式ごとに異なる名称があります。一連の儀式を表す名称と捉える方もいるかもしれませんが、明確な違いと使い分けを理解しておきましょう。
お葬式と葬儀は参列者を招いて読経や焼香などを行い、亡くなった方を弔う儀式のことです。どちらも同様の儀式を表す言葉だと認識してよいでしょう。
通夜はお葬式や葬儀の前夜、夜通し灯りを灯し続けて故人を見守る儀式です。遺族にとっては故人との別れをする大切な時間でもあり、遺族と故人のために設けられる空間ともいえます。最近は半通夜といって夜通しではない形式をとることがおおいです。
ただし現代では、通夜や葬儀を含めた全体の流れをお葬式と表現するケースもあります。お葬式に参列する場合は、同行する知人と齟齬が発生しないよう、お葬式の指す意味を一度確認しておくと安心です。
主だったパターンは以下の3つです。
- 一般葬 … 友人や同僚といった参列者を広く招く
家族葬 … 親族のみで行う
直葬 … 通夜や葬儀を行わない
家族葬や直葬の場合でも、とても親しくしていた知人を招くことがあります。その場合は香典が必要かどうか事前に確認を行う必要があります。一般葬では当たり前のマナーである香典が、かえって迷惑になる場合もあります。
お葬式の服装について
お葬式では一般的に喪服や準喪服の着用がマナーとされています。状況にあわせて判断できるよう、服装のマナーを確認しましょう。
弔問に伺う場合
訃報を受けてから自宅に訪問したり、お葬式で遺族にお悔やみを伝えたりするのが弔問です。自宅への弔問では過度にカジュアルな服装は避けた平服を着用します。喪服はかえって「訃報を待っていた」と捉えられる可能性があるため、避けましょう。男性はスーツやジャケットとスラックス、女性はアンサンブルやスーツなどが一般的です。
葬式に参列する【男性の場合】
着用するのは、ブラックスーツといわれる準喪服です。遺族よりも格式の高い服装はマナー違反と捉えられるため、モーニングなどの正喪服の着用は避けましょう。
注意としては、黒色のスーツ全てがブラックスーツではないという点です。ビジネスシーンで着用するスーツは、全体が黒色であってもお葬式には適しません。色の濃さや生地の質、光沢などが異なる為、購入する際は目的に合ったものを選びましょう。シャツは白色無地を着用します。ネクタイと靴は黒色で、ネクタイピンは不要です。汚れた靴を履いたりしないよう注意が必要です。
葬式に参列する【女性の場合】
マナーとして適した準喪服はブラックフォーマルといわれます。黒色のワンピースやスーツ、アンサンブルなどを着用するのが適切です。スカートの丈は膝が見えない程度の長さがよいでしょう。
靴とストッキングはともに黒色を着用し、高すぎるヒールは避けます。派手な髪型で参列しないよう、事前に整えることも大切です。貴重品を入れるバッグを持ちたい場合は、光沢や派手な柄がない小さめのサイズを意識しましょう。結婚指輪以外のピアスや指輪などのアクセサリーは外してから参列します。ただし、真珠のネックレスやイヤリング、ピアスであれば問題ありません。
その他アイテムについて
傘やバッグなど、参列に必要なアイテムは持参しても問題ありません。どのようなアイテムでも、派手な色や柄が施された物は避ける必要があります。殺生のイメージが強く、お葬式の場では不適切とされるため、動物の毛皮を使用したバッグや、それを連想させる物も着用しないほうがよいでしょう。目につきやすい服装だけでなく、持ち物やアクセサリーも十分に注意して参列しましょう。
冬季に参列する場合、準喪服のみでは寒く感じるかもしれません。お葬式に適したコートやセーターを着用しましょう。柄のない黒色の物であれば問題ありません。黒色のコート類がない場合、なるべく暗い色(グレー/深い紺色)を選びます。カジュアルな印象を与えるダウンジャケットなど派手な上着の着用は、遺族や他の参列者に不快感を与える可能性があります。
お葬式の香典について
亡くなった方に対し、お香の代わりに供えるのが香典です。遺族に渡す香典は、故人との関係性や立場によって適切な金額が異なります。不祝儀袋にも複数の種類があるため、包む金額や状況に合った物が選べるようマナーをおさえておきましょう。表書きを書くための道具選びや、お札への配慮も重要です。
香典の金額
参列者と故人の関係性によって適切な金額が変わるため、以下を参考に大まかな目安を把握しておきましょう。
- 両親 :10万円前後
- きょうだい :3万円~5万円
- 親族(その他):1万円~3万円
- 勤務先・友人など:5,000円~1万円
地域によって金額の相場が異なることも多いため、遺族の考え方も尊重した上で渡せるように準備しましょう。金額を決める際は、死や苦を連想させる4や9がつく金額は避けます。
御霊前と御仏前の違い 葬儀に参列するからには必ず知っておきたいところです。知らなかったからといって間違えてしまうと、失礼になってしまいます。どんな違いがあるのか、おさえておきましょう。 四十九日の前か後か、また宗派の違いによっても異なりま[…]
不祝儀袋の選び方
- 3,000円~5,000円:水引が印刷されているタイプ
- 1万円~2万円:黒白の水引が結ばれているタイプ
- 3万円~5万円:双銀のあわじ結びの水引がついたタイプなど、きちんとした印象のもの
- 10万円以上:大金封
御霊前などの表書きが記された下部には、贈り主が分かるよう名前を記載します。文字は薄い墨で連ねるのがマナーです。故人を偲んで流れた涙で墨が薄くなった、突然の不幸に急いで駆けつけるために墨を十分にする時間がなかったというような意味合いが込められています。
人数によって書き方が異なるため、以下を参考にしましょう。
- 1人:中央に縦書き
- 2人:年長者を右側に記載
- 3人:中央に代表者、その左側に他2人の名前を記載
- 4人以上:表には代表者名と外一同とだけ記載。別紙に他の方の名前を書いて包みに入れる
- 会社名を記載する場合:中央右寄りに小さい字で書く
不祝儀袋は、故人の宗派に合わせた種類を用いる必要があります。代表的なものを紹介しますので、失礼にあたらない物を選びましょう。
・御佛前(浄土真宗)
・御香典
・御香料
・御玉串料
・御榊料
・御花料
金額によって選ぶ種類が異なる点もおさえておくと安心です。宗派が確定できない場合や、無宗教の場合は「御霊前」を選ぶとよいでしょう。
お札の選び方
香典として渡すお金を用意する場合は、新札でない物が適切とされています。新札はあらかじめ用意していたと捉えられる可能性があるためです。近年では厳密にマナー違反とするケースは減っていますが、新札しか用意できなかった場合は折り目を付けてから包みましょう。
ただし、極端に古さを感じさせるお札は適切といえない為、破れてしまったり、汚れが目立ったりしているものも避けましょう。
香典の渡し方
香典はふくさに包んだ状態で持参します。ふくさの色は紺やグレー、深緑などの寒色系で、結婚式などで使われる赤やオレンジなどは避けましょう。紫は慶事、弔事ともに使えるので便利です。
通夜と葬儀両方に参列する場合は、どちらかで一度だけ渡します。以前は葬儀に持参するのが正しいとされていましたが、最近は通夜が重視される傾向にあるため、どちらも参列するときは通夜で渡したほうがよいでしょう。二度渡すのはマナー違反とされるので注意が必要です。
お葬式の挨拶について(例文あり)
お葬式では受付や遺族との対面でお悔やみの挨拶をします。不慣れな場や使い慣れない言葉に焦ると、意図せず避けるべき言葉を発してしまうかもしれません。そのような事態を避けるためにも、失礼な印象を与えない例文やマナーをおさえておきましょう。死の再来を思わせる言葉や、遺族に負担をかける挨拶にも注意が必要です。
お悔やみの言葉の例文
遺族に言葉を告げる際、特に意識したいのはシンプルで伝わりやすい言葉です。故人との思い出話などを語らうのは一連の儀式が終わった後にして、まずは簡潔に伝えましょう。以下が代表的な例文です。
・このたびは、心よりお悔やみ申し上げます。
・生前はお世話になりました。本当に残念でなりません。
・安らかな眠りをお祈り申し上げます。(キリスト教の場合)
・御安霊の安らかならんことをお祈りします。(神道の場合)
焼香のやり方
焼香の具体的な方法は宗派によって異なりますが、まずは以下の一般的な流れを把握しておきましょう。参列者が多い場合には1人1回で済ませるケースもあるため、会場で指示があるときはスタッフの案内に従います。
・焼香台の1歩手前まで歩く
・祭壇に向かって合掌・一礼
・抹香(まっこう)をつまむ
・抹香を香炉の中に落とす(1回~3回繰り返す)
・遺影に合掌・一礼
・そのまま2歩~3歩下がって遺族に一礼
・自席に戻る
参列できない場合
お葬式の案内があったにもかかわらず、事情があり参列できない場合は早めに遺族へ伝えましょう。お悔やみの気持ちを伝えるには、弔電を送るとよいでしょう。
香典を渡す場合は香典を代理人に託すのもひとつの方法です。郵送で送る場合は手渡しと同様に不祝儀袋に包み、現金書留でお葬式の会場や喪主の自宅に送ります。郵送する場合はお悔やみの言葉と参列できないお詫びを記した手紙を添えるとよいでしょう。