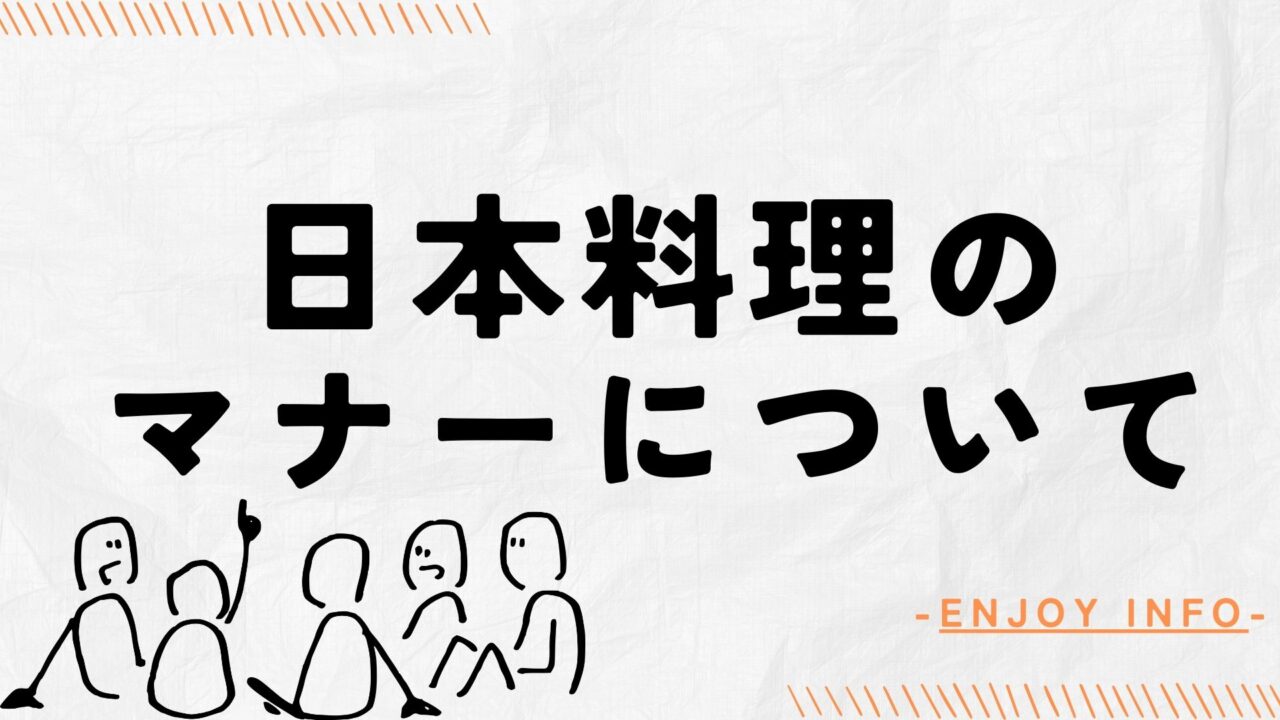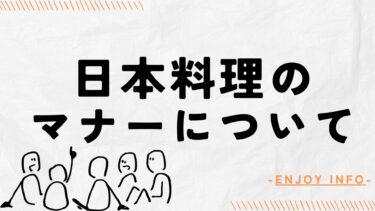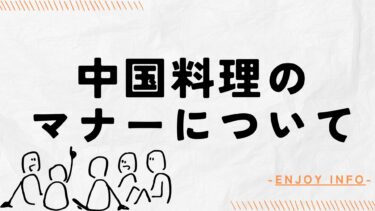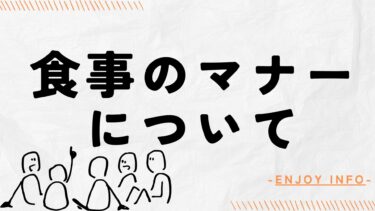日本料理の美しい頂き方
料理の美しいいただき方です。
(前菜)
懐紙で受け取るか、器が小さければ器を手に持っていただきます。
(吸い物)
左手で椀を押さえて、右手で蓋をとります。蓋についたしずくは
椀の中に落としてから上向きにして左手で受け、右手に持ち替えて右側におきます。
吸い物以外でも蓋物は同様にします。
蓋は受け皿代わりにして使用することもできます。一口汁を吸ってから椀種を頂きます。
いただき終わったら蓋を元通り椀に戻します。
(生物)
味がついていることもありますが、醤油を入れた小皿(猪口)が添えられています。
わさびなどは醤油に溶かず、刺身につけてから、醤油を少しつけて、猪口を持って口に運びます。
(焼き物)
魚が一般的で、切り身と尾頭付きの場合があります。
切り身は箸から一口大にとりわけながらいただきます。尾頭つきの場合は、ひれをはずし、頭のほうから取り分けます。
肩身をいただいたら、裏に返すことなく、骨を浮かしてはずし、下の身をいただきます。
いただきにくい魚には、おしぼりが添えられていますので、指を使ってもかまいません。
骨など残った物は中央に集めて、懐紙をかぶせます。
(煮物)
蓋があれば吸い物の要領で取り、箸で一口大に切り分けていただきます。
汁があれば、器を持って合間に味わいます。
この後、揚げ物、酢の物、茶碗蒸しといった強肴が出される場合がありますが、
それで料理が終わりますので、お酒はここまでとします。
(ご飯、留め椀、香の物)
左にご飯、右に留め椀、向こうの中央に香の物が出ます。
ご飯のお代わりは、一口ほど残して茶碗を差し出し、箸を置いて待ちます。
ご飯がよそわれてきたら再び両手で受け取り、一度膳を置き、改めて持ち直していただきます。
受け取った茶碗を、そのまま口に運ぶのは「受け食い」「受け取り」といわれタブーとされています。
(果物、水菓子)
たいていはすぐにいただけるように処理されていますが、
ぶどうのように種が口に残るものは、懐紙に取り出します。
みかんの袋は皮に取り出し、最後に小さくまとめて懐紙に包みます。
日本料理の散会までのマナー
食事を美味しくいただいたあと、散会までもスマートに振る舞いたいものです。
水菓子(果物)をいただくと食事もおしまいです。
それまでは中座をせず、タバコを吸う方もそれまでは遠慮するのが礼儀です。
前礼と後礼で感謝の気持ちを伝えましょう。
前礼とはお食事に行く前に主催者に招いていただいたことへの御礼です。
また後礼はお食事に行った3日以内にお礼を出します。
内容は、『お店の雰囲気が良かった』、『お食事がおいしかった』、『お店(お部屋)から見得る景色が良かった』など具体的に書きましょう。
お食事をする時だけでなく、前後も周りへの配慮や心配りを大切にしたいものです。
懐紙の使い方
懐紙の使い方を紹介します。
①受け皿の代わりとして使う(二つ折りにし、折り目を自分に向けて使います)
②口や指を拭くときに使う
③口元を隠すときに使う(魚の骨を出すときなどに、懐紙で口元をかくします)
④焼き魚の中骨を外すときなどに、魚を押さえる時に使う
⑤食べ終えた後の魚の骨や残骸を隠すときに使う
⑥杯や箸を拭う時に使う
和食の上級者アイテムとして、さりげなく懐紙を使うことで、
スマートで美しい印象を与えることができます。
ビジネスシーンでの会食の場でも、好印象を与えることができます。
日本料理のマナー
結婚披露宴やコース料理で会席料理が出ることがあります。
日本人であれば日本料理のマナーも身につけていたいものです。
【服装】
ミニスカートやジーパンはNGです。
座敷の場合は足を崩しても相手に分かりにくいフレアースカートが望ましいでしょう。
【装飾品】
長い髪の毛はまとめましょう。
テーブルや食器を傷つける可能性のある長いネックレスや指輪は外しましょう。
ダイバーズウォッチもお皿を傷つける可能性があるので適しません。
コートは入口で脱ぎ、着る時も同様に入口で着ます。 座敷やお店の中ではコートを着ません。
大きな荷物は受付で預かってもらいましょう。
【香水】
料理は五感で楽しむものです。料理の香りを邪魔する香水やタバコは控えましょう。
【携帯電話】
携帯電話の電源は切るかマナーモードにしておきます。
相手に気を遣わせるのはマナー違反です。
【中座】
中座をしないためにも、食事の前にはトイレに行っておきましょう。
礼法の言葉に「共に和していただく」という言葉があります。
テーブルマナーのポイントは食を共にして楽しむことです。
度々中座するのは失礼になりますので気をつけましょう。
正しいマナーを身に付け、楽しくおいしくお料理をいただきたいですね。